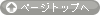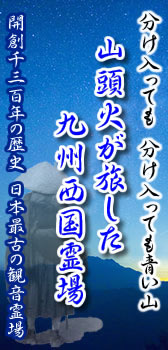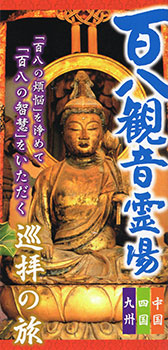祈りの聖地こころの観音霊場・仁比山護国寺 地蔵院
『命の尊さ』−この世界では、天災、テロや戦争、事故や病気などで日々多くの命が失われています。大切な人との死別は、とてもつらく悲しいものです。しかし、その悲しみは永遠のものではありません。今は亡き愛する人を思い、日々祈りを捧げ、今日1日生かされ支えられた命に感謝いたします。
仁比山地蔵院は、豊かな自然の中に素朴な佇を見せる こころの寺。
開創1300余年の歴史を伝える日本最古の観音霊場九州西国観音霊場の第20番札所としても知られています。
毎月17日には観音様の縁日が開かれ、護摩修法、大般若祈祷、法話が行われ、近隣の人々の信仰を集めています。
2月の本尊 十一面千手千眼観音菩薩様の縁日 護摩祈祷はお休みです

平成28年11月 恵比寿天建立

★平成28年11月 恵比寿天建立★
平成28年11月に皆様のご健康と安全、商売繁盛を願い、恵比寿天を建立いたしました。
七福神中で唯一の日本の神様。
いざなみ、いざなぎの二神の第三子といわれ、満三歳になっても歩かなかったため、船に乗せられ捨てられてしまい、やがて漂着した浜の人々の手によって手厚く祀れたのが、信仰のはじまりと伝えられています。左手に鯛をかかえ、右手に釣竿を持った親しみ深いお姿の漁業の神で、特に商売繁昌の神様としても信仰が厚いです。
天井画「花丸」

★平成28年申年本尊御開帳記念 天井画「花丸」★
平成28年申年本尊御開帳記念として、天井画「花丸」(54枚)を奉納させて頂きました。
四季折々の美しい花々のもとで、ご参拝頂ければ幸いです。
檀信徒の皆様、ご寄進下さり誠にありがとうございました。
心より御礼申し上げます。
2月の行事のご案内
- 2月4日(水):星祭り護摩祈祷(参加自由)
午後13時〜開運厄除けの護摩祈祷、大般若点読祈祷、豆まき、法話、星札お渡し - 2月17日(火):観音さまの縁日 お休み致します
今月の護摩祈祷法要は、お休み致します。
縁結び、安産の願いを聞き入れてくれる仏さま。神埼市重要文化財指定の六地蔵塔

平成23年3月31日に市重要文化財に指定されました。
地蔵院境内に立つ石塔。
六道(地獄道、餓鬼道、畜生道、修羅道、人道、天道)における死後の救済を求めて作られたもので、中世以降に流行しました。
永正十四年(室町時代)に吉祥院の別名、寶淋坊(ほうりんぼう)とも呼ばれていたお寺の修業僧が自分の死後の冥福のために供養塔を立てました。
石塔には「奉造立六地蔵所、永正十四天(1517年)丁丑八月廿七日一再中興蕣慶」と刻まれた姿のまま長い歴史を物語っています。
現在の地蔵院の地は元々は吉祥院とういうお寺があり、地蔵院は明治維新前までは九年庵の地にありました。
維新後、神仏分離による貧困の中、吉祥院の土地を持っていた実業家伊丹弥太郎により土地交換が行われ、吉祥院の境内にあった六地蔵塔はそのまま地蔵院が引き継ぐことになりました。
傘の下には六地蔵尊がお祀りされ、参拝者の願いを聞き届けておられます。
縁結び、安産の願いを聞き入れてくれる仏さまです。
真言(しんごん):
オンカカ カビサマ エイ ソワカ